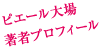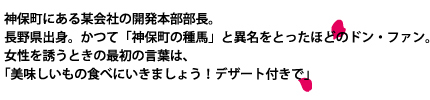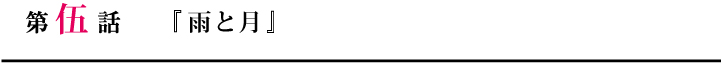『身のうさは人しも告げじあふ坂の
夕つげ鳥よ秋も暮れぬと』
涼川小夜子が、諳んじると、隣の席の
秋山美恵は、すかさずこう訳した。
「我が身の憂いを、遠い場所にいる夫に告げるすべはない。
せめて、「逢う」と鳴く夕づけ鳥よ、
私たちの約束の秋が過ぎ去ってしまうと、夫に、伝えておくれ」
「美恵、さすがね。なんでも知ってるのね」
「ううん、たまたま読み返していただけ。上田秋成の『雨月物語』」
「男の身勝手な話よね。奥さんの宮木は、死してもなお、夫を待ち続けた」
「でも、約束の秋っていう感じがいいよね。確か、宮木、最後の句は、こうよね」
そういって、今度は美恵が諳んじた。
『さりともと
思ふ心にはかられて
世にもけふまでいける命か』
「それでも、いつか、きっといつか、夫は帰ってくる
そう思ううちに、ついにここまで生きながらえた」
美恵が淡々と訳す。
「死んでもなお、夫を想い続けるか…」
二人は、神保町のボンヴィヴァンのカウンターでワインを飲んでいた。
美恵は雑誌の編集者。江戸時代の作家を好んでいた。
小夜子の古書店に通ううちに、仲良くなった。
「で、どうなの?」
美恵がたずねる。
「どうって?」
小夜子は、もったいつけるように聞き返す。
「竹下さんとは最近」
いいかけたそのとき、
ドアが開き、黒縁メガネの彼が、店に入ってきた。
「どうも」と軽く頭を下げる。さわやかでクールな微笑み。
美恵は、ガタっと椅子を降りる。
「じゃあ、私はそろそろ会社に戻らないと……校了あるし」
「いいじゃないですか。ちょっと寄ったら偶然会っただけです。
三人で飲みましょうよ」
竹下の声が体に響く。
彼の声には、魔力がある。不思議な波動に、ゆさぶられる。
「そうよ、美恵、一緒に、飲みましょう。あと一時間くらい、
いいでしょ?」
小夜子が、いじわるな笑顔になった。
楽しんでいる。
今夜の二人の逢瀬に、私が使われる、美恵はそう思った。
「『雨月物語』には、哀愁がありますよね。人間本来の業が描かれていて…」
竹下が言った。
美恵は想像した。今、私をはさんで並んでいるこの二人が、触れあう姿を。
小夜子は、そんな彼女の様子に気づいたかのように、
こう言った。
「日常には、闇がひそんでいて、それを誰も払いのけることはできない。
ただ受け入れるしかない。上田秋成は、そう言っているように、
私は感じる」
「やっぱり、そろそろ行かなくちゃ」と美恵が席を立った。
出ていくとき、閉じる寸前のドアから竹下が小夜子の髪をなでるのを
見た。
細くて白い指が、さあっと真っ直ぐ下に、落ちた。
小夜子は、こっちを見て、薄く微笑んだ。
外は、雨だった。
秋の冷たい、雨だった。
美恵は足早に、路地を行き、暗闇に消えた。
黒い猫が目を細めて、その行方を追った。
その瞳はまるで三日月のように、妖しく光った。

秋山さんの瞳は、深くて強い。 いつも何かを探しているような、瞳。 でも、笑うと一瞬でまわりの空気を変える。ふわっと包み込む。 「このひとのためならやらなくちゃしょうがないか」と、思う。 不思議な波を持った女性。そんな彼女が校正紙に赤字を入れる。 その手は、彼女の波を伝え、波と共に揺れる。 やがて素敵な作品が世の中に拡がっていく。
- 第百八話(最終回)『さくらが、濡れるとき』
- 第百七話『色、匂い、そして温かみ』(中華そば 伊峡)
- 第百六話『そこに、父が、いた。』(あたらくしあ)
- 第百伍話『元旦や、人間だけがあらたまる』(無用之用)
- 第百四話『ゆびではじいて、そう、小豆を、揺らして……』(無用之用)
- 第百参話『郡上の夜は、明けない』ナビブラ神保町
- 第百弐話『猫娘の舌ざわりと、一反木綿のうねり』明治大学米沢嘉博記念図書館
- 第百壱話『本能的な女と、壁をつくる男』(ARTイワタ)
- 第百話『男4人に、かこまれて……。』スイーツメディアufu.(ウフ)
- 第百話『男4人に、かこまれて……。』スイーツメディアufu.(ウフ)
- 第九十九話『穴をふさぎ、穴を開く』(かふぇ あたらくしあ)
- 第九十八話『しっぽは、心をかくせない』(みわ書房)
- 第九十七話『手でやる? それとも道具を使う?』(ジェオ)
- 第九十六話『内なる奥底に取り込まれた蛍石のように』(薫風花乃堂)
- 第九十伍話『30秒、蒸らしてから……豆をほぐす』豆香房(神保町店)
- 第九十四話『落ちる実、もしくはだれでも一度は処女だった』(元)鶴谷洋服店
- 第九十参話『かきまわしたり、ときに刺したり、またかきまわしたり……』(桜日和)
- 第九十二話『ハートスナイパーは、ローズのつぼみを隠している』(CANDY BOUQUET)
- 第九十一話『あなたの、頑丈な、チューブが、私を、変える』ONNON(オンアンドオン)
- 第九十話『クリが、嫌い、でも、クリが、好き』ufu.(ウフ。)
- 第八十九話『太いギンポは、穴に入り、穴から出てくる』(しゃれこうべ)
- 第八十八話『沈み始めるまで、5秒以内』ワイン食堂 ChatGatto(シャガット)
- 第八十七話『金が光る、嫉妬の焔(ほのお)』(神田伯剌西爾)
- 第八十六話『最初は劣勢でも、巻き返せるときが来る』(共同書店PASSAGE)
- 第八十伍話『姿は見えなくても、確実にそこにいるもの』(ギャラリー珈琲店 古瀬戸)
- 第八十四話『だんだん、じょうぶに、なりました』(「澤口書店 巌松堂ビル店)
- 第八十参話『こぼれる、このままでは、こぼれてしまう』(あるまっぷCHIYODA)
- 第八十二話『的の中心を狙わず、穴に直接入れること』(HSTチャンネル)
- 第八十壱話『三つの穴を、埋めるもの』(大和屋履物店)
- 第八十話『運河のように、ひとという名の船が行き交う場所』(喫茶プペ)
- 第七十九話『澱が拡がる~スノードームのように』(カフェ・トロワバグ)
- 第七十八話『空っぽなリンゴ箱の中に、たくさん詰まっているもの』BOOK SHOP無用之用
- 第七十七話『イルカのメロンは、ぷにゅぷにゅ話す』LAULE’A(ラウレア)
- 第七十六話『黒すぎる黒、白すぎる白』(文房堂)
- 第七十伍話『赤い旋律、ジャズの吐息』( JAZZ OLYMPUS!)
- 第七十四話『悶々、ホルモン……何度も転がして』(十勝ハーブ牛ホルモン MONMOM)
- 第七十参話『虞美人草の花の蜜』(おさんぽ神保町)
- 第七十二話『雄のリズム、雌のメロディ』(イリアフラメンコスタジオ)
- 第七十一話『屋根をつたう、しずく……』(加賀亭みなみ)
- 第七十話『左人差し指は、棹に対して、直角に……』(三味線と小物の店 音福)
- 第六十九話『凹凸が、織り成す色』(PRIMART/プライマート)
- 第六十八話『もちもちで、しっとりしているもの』(@ワンダー&ブックカフェ二十世紀)
- 第六十七話『入れる、入れないは、問題ではない』(リリパット/Book House Cafe)
- 第六十六話『象の鼻は、筋肉で出来ている』(バンコックコスモ食堂)
- 第六十伍話『箱のおもむき、骨のたしなみ』(三慶商店)
- 第六十四話『茹でたもの、蒸したもの、焼いたもの』(スヰートポーヅ)
- 第六十参話『男坂と女坂の、あいだにある坂』(男坂・女坂)
- 第六十弐話『路地裏の赤い哀しみ』(神田すずらん通り)
- 第六十壱話『マサラ~混ざり合うということ』(インドレストラン マンダラ)
- 第六十話『男と女の点と線』(洋食膳 海カレー TAKEUCHI)
- 第伍十九話『桜と抹茶の間に揺れる』(庭のホテル 東京)
- 第伍十八話『メロンのようなカボチャが、口の中で溶ける』(気生根-Kifune)
- 第伍十七話『外はカリっと、エッグタルトのように』(ポルトガル菓子店「DOCE ESPIGA」)
- 第伍十六話『投げるひと、打つひと、それを見ているひと』(古書『ビブリオ』)
- 第伍十伍話『君によく似た柔らかい陽射し』(cafe&dinning『HORIZON』)
- 第伍十四話『漂流酒場で漂流する』(海文堂「漂流酒場」&「ランチカレー」)
- 第伍十参話『好きだったひとの、かほり』(神保町ブックセンター)
- 第伍十二話『ダナンの龍が火を噴くとき』(神保町「酔の助」)
- 第伍十壱話『アライグマの毛皮を着た男』(SOUP DELI)
- 第伍十話『こじれたひとが、好き』(虔十書林)
- 第四十九話『いつでも着替えられる状態にしておく』(ホワイトカレーと焼酎のお店「神田ゲレロ」)
- 第四十八話『ストレスは風味を落とし、色をくすませる』(flat Grill&Wine 神保町)
- 第四十七話『同じ場所で同じ風景をもう一度見ることは、できない』(カフェ ティシャーニ)
- 第四十六話『手札の順番を変えてはいけない』(すごろくや)
- 第四十六話『手札の順番を変えてはいけない』
- 第四十伍話『能面は、知っている』(書肆 髙山本店)
- 第四十四話『少女の羽は、夜、開く』(「珈琲舎 蔵」)
- 第四十参話『替え玉がついてくる、人生』(博多ラーメン「めんめん・かめぞう」)
- 第四十弐話『ゾウを飲み込んだ、ウワバミの哀しさ』(欧風カレー ボンディ神田小川町店)
- 第四十壱話『混ざるほどに極みへ向かう……』(欧風カレー ボンディ神田小川町店)
- 第四十話『鳥の目が、見ている……』(永森書店)
- 第参十九話『舌にのせて、味を楽しむ』(Bon Vivant)
- 第参十八話『自分の頭に、身を投げる』(らくごカフェ)
- 第参十七話『恋の温度、ふちの焦げ目』(pizzeria zio pippo)
- 第参十六話『太さと重さを手で測る』(金沢テニスショップ)
- 第参十伍話『猫の尻尾は、つかめない』(猫本専門 神保町にゃんこ堂)
- 第参十四話『入るとき、出ていくとき』(喫茶さぼうる)
- 第参十参話『もつの煮込みと、柔らかいそれ』(加賀亭みなみ)
- 第参十弐話『無限大に響く、スピーカーのように』(JAZZ OLYMPUS!)
- 第参十壱話『濡れた午後と、カフェオレの泡』(ギャラリー珈琲店 古瀬戸)
- 第参十話『三つの線が同時にそこにあるとき』(『お茶ナビゲート』)
- 第弐十九話『ゆっくり急げ』(雑貨『FESTINA LENTE』)
- 第弐十八話『男は、征服した女の寝乱れた顔を、見ている。』(hair&gallerybooks『moloco』)
- 第弐十七話『エックスであってNOではない』(サクラカフェ 神保町)
- 第弐十六話『妖精に出会う夜』(三省堂書店)
- 第弐十伍話『指は嘘をつかない』(神保町花月)
- 第弐十四話『炒め過ぎない』(謝謝)
- 第弐十参話『小さいけれど、精巧な何か』(呂古書房)
- 第弐十弐話:『Sに気づく夜』
- 第弐十壱話:『角度が大事』
- 第弐十話:『鳥は、鳥は、木に眠り』
- 第十九話:『夜の過ちを消せるペン』
- 第十八話:『南の島にいこうよ』
- 第十七話:『Jazzの夜に』
- 第十六話:『手触りの記憶』
- 第十五話:『顔を形作るもの』
- 第十四話:『ネバーエンディング・ストーリー』
- 第十参話:『万葉かるたのささやき』
- 第十二話:『茶色の下に隠れているもの』
- 第十一話:『煮込まない、寝かさない』
- 第十話:『消しゴムでも消せない匂い』
- 第仇話:『古書の香り、不思議の国』
- 第八話:『白い花びらの行方』
- 第七話:『わたしと あそんで』
- 第六話:『三位一体』
- 第伍話:『雨と月』
- 第四話:『仮面の下の顔』
- 第参話:『背徳の智恵子抄』
- 第弐話:『花魁の美人画・裏を返す』
- 第壱話:『春の琴・指の感触』
- 第参十弐話『無限大に響く、スピーカーのように』(JAZZ OLYMPUS!)

- 2021年年月
「あぶらが好きさ」 - 2017年11月
「ナビブラ特集アーカイブ」 - 2015年10月
「第56回「東京名物・神田古本まつりへ行こう!」」 - 2015年09月
「残暑は汗をかいてブッ飛ばせ! 食べ比べ 酸辣湯麺」 - 2015年08月
「人の流れが神田錦町へ続々と! 憩いの広場、テラススクエアへ行こう!」 - 2015年07月
「祝8周年! 末広がりの面白さ 神保町花月」 - 2015年06月
「これなら雨の日が待ち遠しい!? 雨の日グッズ&サービスのあるお店」 - 2015年05月
「チャレンジャー達を応援! 新店舗さん、いらっしゃ~い!」 - 2015年04月
「祝開店60周年! やっぱり「さぼうる」でサボるのが好きっ!」 - 2015年03月
「神保町の新トレンド! これってマジかぁ!? “缶バッチな人”増殖中!」 - 2015年02月
「乙女心をくすぐるスイーツパンの誘惑 メロンパン食べ比べ!」 - 2015年01月
「1年のはじまりは、ズルズルすすって、クイクイ飲もう! 新春は蕎麦屋で日本酒」